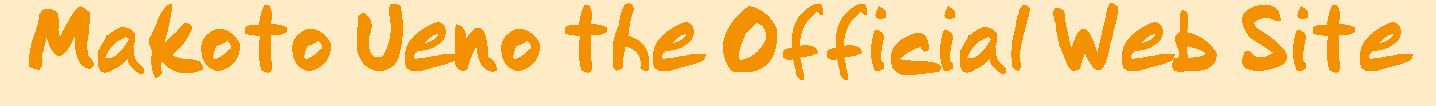Writings
シュトライヒャーのピアノとその製作家一族について
(波多野みどり)
今回の録音における使用ピアノ
オーストリア、ハプスブルク帝国の都、ウィーンを代表するピアノ製作会社であったヨハン=バプティスト・シュトライヒャーにより1861年に製造されたこのピアノは、外装にはローズウッド材が使われ、そこに伝統工法シェラック塗装が施されていて、品格のある高級家具のような存在感を漂わせている。鍵盤蓋を開くと双頭の鷲のマーク、帝室兼王室御用達ピアノ製作家 J. B. STREICHERと記された美しい蔦模様の真鍮象嵌細工のネームプレート、そしてその上の木彫りの繊細な透かし模様の譜面台にも目を奪われる。
総ての弦は、真っ直ぐ平行に張られていて、低音弦には巻き線が使われてはいるものの、弦1本あたりの張力は現代のピアノが70~80kgであるのに対し、このシュトライヒャーの場合は40kg前後である。とは言え、この時代より前のフォルテピアノの倍以上になった張力を木製の本体だけでは保持できなくなり、中音域の両サイドに鉄製の黒い支柱が2本使われている点、そして高音部手前に現代のスタインウェイピアノの様にカポダストロバーも備えている点は、19世紀初頭のフォルテピアノから20世紀以降の現代ピアノへの過渡的なモデルとでも言えようか。打弦システムは、現代のものとは随分異なり、イギリス式とドイツ式の特徴を併せ持つアングロ・ジャーマン式となっており、ハンマーはフェルト製だが、その表面は一枚の皮で覆われていて、独特の音色を生み出している。
ピアノの歴史は、今から遡ること300年余り、西暦1700年頃、イタリアのメディチ家お抱えのチェンバロ製作者バルトロメオ・クリストフォリ(1655-1731)が打弦機構を発明したことに端を発する。弦を打つ力をコントロールすることで音量を自由自在に操ることができるため、グラヴィチェンバロ・コル・ピアノ・エ・フォルテ “Gravicembalo col piano e forte” と名付けられた。
誕生した当初4オクターヴだった音域は、モーツァルト、ベートーヴェン初期には5オクターヴ、シューベルト時代には6オクターヴ、そしてシューマン、ショパン、リスト、ブラームスの時代ともなると音域はさらに拡大した。今回の1861年製シュトライヒャーに至っては7オクターヴ85鍵にまで拡張されており、現代の88鍵とほとんど変わらない。
クリストフォリは羊皮紙を丸めたハンマーを用いたが、モーツァルトやベートーヴェンの頃には薄いなめし皮を何層にも重ねたハンマーが一般的であった。その後、ピアノが大きくなるにつれてハンマーも大きさと質量を増し、ブラームスの頃には、現代のピアノにも継承されるフェルト製へと変化を遂げた。今回の録音で演奏されたシュトライヒャーでは、フェルトのハンマーが、一枚のなめし皮で覆われた構造となっている。そして、ピアノ本体内部構造は、現代のピアノでは閉じられている響板のフロント側の境目が、ウィーンの伝統を守って開口されており、独特の音の響きを生む重要な要素となっている。
シュトライヒャー家のこと
それでは、ヨハン=バプティスト・シュトライヒャー(1796-1871)とは一体どのような人物であったのだろうか。
今日、ウィーン中央墓地といえば、映画「第三の男」のラストシーンで知られる観光地であり、そこには大作曲家たちの墓が集まる一角があって訪れる人も多いが、ベートーヴェンやブラームスなどと並んでピアノ製作家シュトライヒャー家の立派な墓碑があることに気付く人はめったにいない。墓碑の先頭には J. B. STREICHER と刻まれている。その下には彼の両親、父ヨハン=アンドレアス・シュトライヒャー(1761-1833)と母ナネッテ(1769-1833)の名が並ぶ。
シュトライヒャー家のピアノ製作の歩みは、ヨハン=バプティストの祖父の代から始まる。バプティストの母方の祖父は、モーツァルトが激賞したことでも知られる、ドイツはアウグスブルクのヨハン=アンドレアス・シュタイン(1728-1792)である。シュタインは、 ストラスブールで著名なオルガン製作者のゴットフリート・ジルバーマン(1683-1753)の甥ハインリッヒ・ジルバーマン(1727-1799)の下で修業を積んだ後、アウグスブルクに移ってからは様々な鍵盤楽器の製作にあたった。なかでも彼が作り出した軽いタッチのピアノは後にドイツ式(跳ね返り式)と呼ばれ品質が良いことで有名になった。実はモーツァルトが愛用していたクラヴィコードもモーツァルトの父がシュタインに依頼したものである。またボンでヴァルトシュタイン伯爵がベートーヴェンに提供したフォルテピアノもシュタインの手によるものだ。シュタインは、歴代随一の名工としてヨーロッパ中にその名が知れ渡った存在であった。
ヨハン=バプティストの母ナネッテは、幼少の頃にモーツァルトと連弾したというほどのピアノ演奏の腕前の持ち主であったと同時に、当時の女性としては珍しくピアノの製作技術を父シュタインから幼くして学び、20歳の頃にはすでに一人前のピアノ職人となっていた。1792年に父が亡くなると、23歳であった彼女は弟マテーウス=アンドレアス(1776-1842)とともに家業を引き継いだ。その翌年には、ウィーンのピアニストであるアンドレアス・シュトライヒャーと結婚し、これを機に二人の弟たち(17歳のマテーウスと10歳のフリードリヒ)を引き連れてウィーンへ活動の場を移したのだった。
余談ではあるが、夫アンドレアスは、若かりし頃、ゲーテと並び賞されるフリードリッヒ・シラー(1759-1805)(ベートーヴェンの「第九」に引用されている「歓喜の歌」の詞の原作者)の亡命(1782)に同行したエピソードでも知られている。
ナネッテと共同でウィーンでのピアノ製作を開始した弟マテーウスだが、10年と経たずに「アンドレ・シュタイン」という名で独立する。弟との決別により、ナネッテは当時としては異例の女工場主となった。これ以降、夫アンドレアスはシュトライヒャー社の発展に尽力すべく、会社経営のみならず音作りにも積極的に携わるようになった。このようなナネッテ、アンドレアスの奮励がウィーン製ピアノの名声を高めることに繋がったことは間違いないだろう。
シュトライヒャーのピアノとゆかりのある著名人は数多く存在するが、文豪ゲーテもナネッテのピアノを所有していた。若きメンデルスゾーンはこのピアノを大変気に入り、ゲーテのもとに滞在した折には、一日7時間も弾き続けたと言われている。
なにより、ベートーヴェン(1770-1827)が全幅の信頼をシュトライヒャーに寄せていたことは注目に値する。1792年以来ウィーンに定住していたベートーヴェンのもとには、さまざまなメーカーからピアノが贈られたが、シュトライヒャーとの関係はとりわけ親密であった。音楽家とピアノ製作会社という関係性を超え、ナネッテに至っては晩年のベートーヴェンを気遣い、親身に日常生活の世話までしていたことが、シュトライヒャー一族が保管するベートーヴェンと交わされた数多くの手紙からも伺える。ベートーヴェンの死後、この大作曲家の全作品を最初に出版したのは、アンドレアスであった。彼は、ウィーン楽友協会創設メンバーのひとりでもあり、パリのプレイエルやエラールに先立って邸宅内のサロンでコンサートを開催した。また、ウィーンで初めてプロテスタント教会の讃美歌集を出版したことでも知られている。
さて、そんな二人の息子ヨハン=バプティストは、ピアノ製作家としての修行の総仕上げにヨーロッパの主たるピアノメーカー―フランスのエラールやプレイエル、イギリスではブロードウッドなど―で研鑽を積んでウィーンに帰還したのち、1823年にシュトライヒャー社の共同経営者となる。1833年に両親を相次いで亡くしてからは、バプティストがシュトライヒャーの名を背負い、孤軍奮闘することとなった。彼は優れた手腕を発揮し、アングロ・ジャーマン・システムの特許を取得(1831)したほか、1835年から45年の間にウィーンで開催された産業博覧会すべてにおいて金賞を受賞している。1851年にはロンドンの万国博覧会にも出展。そして1860年代には鋳鉄製の一体型フレームと交差弦をシュトライヒャー社のピアノにも採用し、1867年のパリ万国博覧会においてもメダルを獲得するほどまでに躍進を果たした。
バプティストは、規模拡大のため1837年にサロン併設の工場をウィーン、ウンガルガッセに移転させている。ここには、リスト、ショパン、シューマン、ブラームスなどのコンポーザー・ピアニストばかりでなく、他の分野の著名な芸術家も出入りし、コンサートや、ピアノの展示会などが催された。ピアノ製作技術もさることながら、このような先見性が功を奏し、シュトライヒャー社は、ヨーロッパ中の音楽界にその名を轟かすほど重要な地位に上り詰めたのであった。
最初の妻を亡くしたバプティストであるが、1849年にショパンの弟子であったピアニスト、フリーデリケ・ミュラー(1816-1895)と再婚した。彼女は、ショパンが作品46を捧げたことにより「マドモアゼル 作品46」とのニックネームを持つことでも知られている。
シューマンとシュトライヒャー
ここでクララ・ヴィーク(1819-1896)やロベルト・シューマン(1810-1856)に目を向けることとする。クララの父フリードリヒ・ヴィーク(1785-1873)は、モーツァルトやベートーヴェンの父親同様、クララの才能を見越してロマン主義精神に目覚めたピアニストにすべくスパルタ式の英才教育を施したことで有名である。晩年の日記で、クララは自分には楽しい子供らしい時はなかったと回顧している。クララのために父ヴィークは1827年にアンドレ・シュタイン(先述のナネッテの弟マテーウスによるピアノメーカー)のピアノを注文し、公開演奏にもこのピアノを使用した。
当時、偉大なる音楽家かつ教育者として存在感を示していたヴィークの下には、若き音楽家たちが教えを乞い訪ねてきていた。そのうちの一人、19歳の時にヴィークに師事したのがロベルト・シューマンであった。その後、シューマンがウィーンに長期滞在した際にはシュトライヒャーのサロンにも出入りし、そのピアノを好んで弾いていたと言われている。クララのウィーンでの成功を知り、彼の音楽雑誌『新音楽時報』の本拠地をウィーンに移せば、ヴィークから遠ざかり、二人の未来が開けると考えたようだ。しかし、反動保守の政治体制下にあったウィーンではシューマンは歓迎されず、計画を断念するに至った。
1870年のウィーン楽友協会のオープニング記念コンサートでクララが演奏した際にピアノを提供したのもシュトライヒャーであった。シュトライヒャー社には、クララのためのピアノが常に用意されていたという。
シュトライヒャー社の終焉
1828年にはシュトライヒャー社と地元を同じくしてウィーンにベーゼンドルファー社が創業していた。ウィーン産業博覧会での金メダル獲得(1839)や、帝室及び王室御用達ピアノ製作家に選定されるなど、着実にシュトライヒャー社最大のライヴァルへと成長していったのである。その豊かな低音、堅牢なハンマーを持つピアノはリストにも気に入られていた。
一方、シュトライヒャー社では、1871年にバプティストが亡くなると、1859年以来経営に加わっていた息子エミールが後継となった。その間、機械化を推し進めた生産を開始していたベーゼンドルファー社に対して、品質の良いピアノを年間150台余り生産するというシュトライヒャー社の従来のスタンスでは太刀打ちできなくなっていた。ついに、1896年にスティングル社に売却される形で、シュトライヒャー社の幕引きが訪れたのである。
名こそ歴史のものとなったが、ヨハン=アンドレアス・シュタインに始まり、ナネッテ、バプティスト、エミールの4代に渡り紡がれたシュトライヒャー社は、ピアノ製作史上、紛れもなく重大な功績を残した。それどころか、モーツァルトやベートーヴェン、シューマン夫妻をはじめとする名だたる音楽家たちの活躍の軌跡には、彼らを魅了し、音楽人生を支えたシュトライヒャーの魂が確かに刻まれ、今なお息づいているのである。