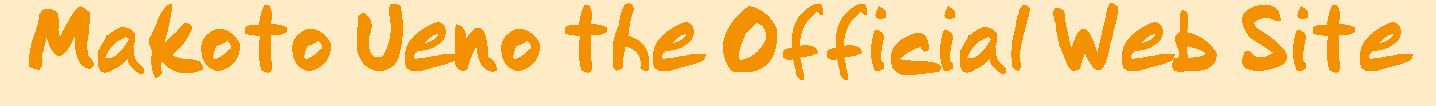Writings
楽器と曲目について一言
今回のソロ・アルバムを収録するに際して、最初期の作品「パピヨン(蝶々)作品2」、成熟したシューマンのピアノ作品中の最高傑作とも言える「幻想曲 作品17」、そしてクララとの結婚直後に出版された「ウィーンの謝肉祭の道化 作品26」という3曲を選んでみました。
シューマンが「パピヨン」を書いた1830年代の初めのピアノと1860年代のピアノは、僅か30年間とはいうものの、それなりの違いがあります。当時ヨーロッパ中の様々なピアノメーカーが、それぞれに工夫を凝らし、大きな変更を加えた時期でもあるからです。
しかし、やや乱暴な言い方になってしまいますが、21世紀の視点から見れば、1820年代ベートーヴェンが使っていたコンラート・グラーフなどと、1860年代のシュトライヒャーの音の親和性、音造りの方向性は、ほぼ「兄弟、或いは親戚のようなもの」であって、現代のピアノと比べると、同じ文化圏のほぼ同時代のピアノと呼んでも差し支えないようにも思います(因みにシューマン夫妻は1830年代のコンラート・グラーフをシューマンが亡くなるまで所有していました。それが後年ブラームスの所有となります)。
シューマンがこの世を去ったのは1856年であることから、そしてシューマン自身、死の直前まで初期のピアノ作品の改訂を行なっていることも多いことを勘案し、ウィーンの伝統的な製法を守り、平行弦で造られたこの1861年製シュトライヒャーのピアノを使ってレコーディングに臨みました。
近年、ショット社からシューマン作品全集が出ましたが、手紙なども含む資料も200年近くが経過して充実し、また謎のように思われていた作品の構成面にも光が当てられ、漸くシューマンの全貌が現れつつある感があります。彼の一生はとてつもなく密度の濃いものだったと想像出来ますが、やはりクララをはじめとする近くにいた家族、友人、知人たちによって、個人的な情報が意図的に遮断されたこともあり、なかなかシューマンの一人の人間としての全体像が現れず、断片的なイメージが一人歩きしていたように思います。
「パピヨン 作品2」は、1829年から31年までの間、彼がまだハイデルベルクで法律を学んでいた時期から、その後ライプツィヒで音楽家としての勉強を専門的に始めた頃に作曲された作品ですが、すでに彼の個性は際立っています。10代の彼に最も影響を与えた小説、ジャン・パウルの “Flegeljahre”(日本では「生意気盛り」他、色々な邦訳邦題がありますが、1804-1805年に出版された当時、最もドイツ的な精神を表した小説と言われました。内容の複雑さから翻訳が最も難しい作家の一人でしょう。恒吉法海氏の翻訳の偉業には脱帽です)に直接の影響を受けて書かれました。1832年4月にライプツィヒのキストナー社により出版されました。
「幻想曲 作品17」は、シューマン自身がそれまで書いたものの中で最も充実した作品と述べたもの(特に第1楽章)で、凝りに凝ったモチーフとテーマの使用、細部までの拘りを見せた、意欲的な「幻想ソナタ」とも言える作品です。もともとはボンのベートーヴェン記念碑の建立案にインスパイアされた作品でした。
シューマンの幻想曲は、ベートーヴェンの歌曲 “An die ferne Geliebte(遠くにいる恋人へ)” を強く念頭に置いたもので、そのメロディーは直接引用されています。記念碑の建立に最も貢献し、この作品を見事に弾いたと伝えられているリストに献呈されました(ただしリストの演奏は、シューマンが想像していた音楽とは違っていたそうです)。
1835年と36年を中心に、その後数年かけてライプツィヒで作曲され、1838年10月からのウィーン滞在中にも手が加えられ、最終的に1839年4月にブライトコップフ社により出版されました。
将来、クララとの結婚生活を始める為にはライプツィヒを離れねばならない、というヴィークの出した条件を考慮しなければならなかったシューマンは、1838年10月から1839年4月まで、その下調べのためにウィーンに滞在していました。「ウィーンの謝肉祭の道化 作品26」は、それがきっかけとなって1839年3月頃から取り掛かり、ライプツィヒに戻ってからも作曲が続けられ、1841年にウィーンの出版社ミケッティ社から出されたものです(ちなみに同年、全く同じ出版社からメンデルスゾーンの「厳格なる変奏曲 作品54」、そしてショパンの「ポロネーズ 第5番 嬰ヘ短調作品44」、「前奏曲 嬰ハ短調 作品45」なども出版されています。また、同じくショパンの「演奏会用アレグロ 作品46」も同時期に別の出版社から出版されていますが、こちらはウィーンの女流ピアニスト、フリーデリケ・ミューラー、ショパンの弟子でもあり、そして1849年以降にヨハン・バプティスト・シュトライヒャー夫人となる女性に献呈されています)。
この作品は、クララから「演奏会のために華麗で聴衆に分かりやすい作品を作ってほしい」との希望により作曲されました。全体としては非常に健康的な、明るいピアニズムが支配的な作品で、5楽章形式のソナタとも言えるでしょう。副題には “Fantasiebilder(幻想絵画集)” と、E.T.A.ホフマン風のタイトルがついています。なおオリジナル・タイトルの “Faschingsschwank” というのは、通常は謝肉祭(の道化)と訳されていることが多いですが、謝肉祭の茶番劇とか、謝肉祭の(空)騒ぎも意味するようです。
上野 真