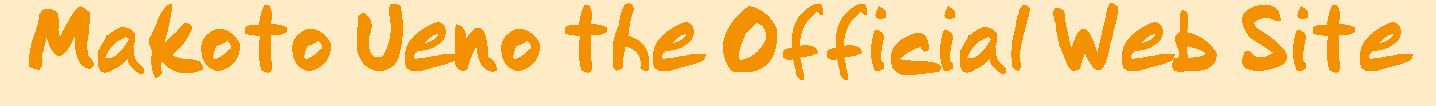Writings
ピアニストの原点としてのバッハ平均律クラヴィーア曲集
歴史に残る芸術作品でありながら教材でもある、鍵盤楽器(ピアノ)奏者にとって最重要な作品集、それが2巻にわたる平均律クラヴィーア曲集である。1巻と2巻ではほぼ20年の作曲年の開きがあるが、これらは300年の間、価値を失うどころか益々深い意味と輝きを増している。
往年の名ピアニスト、シュナーベルは「演奏可能なレベルよりも常に優れている作品」を演奏したいと語っていた。バッハのこの作品はその代表例であると思う。
個人的な話になるが、1970年代後半、私が中学生になった頃、原田光子訳「大ピアニストは語る」という、その時点から見てもかなり昔に出た本を見つけて読んでいたことがある。
また同じ頃、東芝EMIから出ていた「鍵盤史上に輝く不滅の巨匠達」とタイトルが付けられたレコードで、録音を残してくれた19世紀生まれの過去のピアニストたちのことを知ってその系譜を調べたことがあった。
その時に印象的だったのは、パハマンやバックハウスがバッハを弾くことの重要性を語っていたことだ。
バックハウスがスケールやバッハを必ず毎日弾くと言っていたのは有名な話で、チェリストのカザルスも毎朝の日課としてピアノの前に座って平均律クラヴィーア曲集を弾いていたこと、コルトーが、毎朝手紙を書いたり読んだりする前、必ずバッハとショパンの練習曲を弾いていた逸話等、そのような話は枚挙に暇がない。
シューマンが「若い音楽家への助言」の中で「毎日バッハを勉強する様に」と書いていたことは、当時の私にとって深い印象を与えた。
私の父はアマチュアながら60年以上もオルガニストとして無償奉仕を続け、殊にバッハとバッハ以前の音楽に関心が深かったので、日常的にもバッハの話を聞かされて育った。
その大切さを朧げながらわかっていたものの、実際「バッハを毎日弾くこと」を実行に移すようになったのは、留学を終えて日本に帰ってきた25歳の頃からであった。学生生活から離れ、技術面や音楽の捉え方について、もう一度勉強をやり直したいと考えての再スタートであった。
平均律クラヴィーア曲集を日々の練習の糧とするようになってから30年以上が経つ。長年付き合ってきた友人たちの様な曲集である。
バッハを繰り返し弾くことによって、やはり作曲法全般、和声、対位法、旋律線、リズム、装飾音、そして楽譜に書いていない事柄などが少しずつ自然に感じられ、理解できるようになってきた。
多様な音型を意識するきっかけになり、様々な指遣いの可能性や手の重心の置き方、現代ピアノにおける腕や上半身の使い方、5オクターヴという限られた音域の中での基本的な響きの作り方などを、作品自体が色々と教えてくれたし、これからも教え続けてくれると思う。
これ程までに教材的にも芸術的にも奥行きのある作品は少ないだろう。全く飽きることがない。
— 今回のレコーディングについて —
バッハと言うと、一般的には何か遠くにある様な、偉大な歴史上の人物、完璧な作曲家、学校の教室に飾られている古めかしい肖像画の通り、現代とは関係のない作曲家というようなイメージがあるような気がする。
今回、このアルバムを録音するにあたって、何か拘り抜いた解釈の新基軸を提示するとか、新しい奏法を探求し、何か驚きを持って迎えられるようなアプローチを探求するなどのプランはなかった。
それが正しいかどうかは別として、現代のピアノで普段から弾いている様に弾くこと、不要な自意識や虚飾を出来るだけ取り除き、一緒に暮らしを共にしてきた、色々なことを教えてくれた、完璧でありながら人間味あふれる一作品として、自分なりに誠実にバッハの作品に向かい演奏することを最優先とした。
音楽家、演奏家というものは、多少の自尊心がないと務まらない職人的な職業だが、音楽家の神とも言えるバッハの前では、自分を飾ることもできない。より良く見せようなどと考えるのは無益なものだ。
或いはそれとは逆に、バッハが偉大過ぎて自分の様な凡人の手には負えないと考えてしまうと、折角作曲者がこの作品に託した目的、つまり「学習のため、喜びのため」という本来の意図から外れてしまうことにもなる。
バッハがいつも心に留めていた通り、最終的には神(或いはミューズ)の為にというクレド、そして自分なりのやり方で作品により近づくことが求められているように感じる。
楽器の選択を始め、アーティキュレーション、テンポ、ダイナミクスのニュアンス付けなど、バロック作品を現代に演奏する時には様々に異なる考え方、アプローチ、解釈、演奏法があることだろう。オリジナルに忠実な楽器で、当時の文献を読み込み、その上で様式的に破綻のない様に演奏する…それが現代の主流であるのは承知している。
同じ二段鍵盤用の作品でもオルガン、クラヴィコード、チェンバロを弾くのでは全く異なる弾き方が求められる筈で、実際作品によって複数の楽器の使い分けをして演奏する試みも行われた。例えば1980年代にダニエル・コルゼンパが上記の3種類、近年では野平一郎が コンピュータを含む3種類の楽器を使って録音をしている。
バッハはその時代、身近に存在した楽器のためにこれらの曲集を作ったのは揺るぎのない事実だが、殊にオルガン、鍵盤楽器についてのエキスパートだったこともあり、将来のどのような鍵盤楽器においても、音楽的価値が失われないような、ある意味普遍性のある作品を作ったのではないかと私は想像している。
クラウディオ・アラウは、若い頃にバッハの全作品をピアノで弾いていたピアニストであったが、晩年に「再びバッハを演奏しないのか」と訊かれ、「バッハやスカルラッティはチェンバロで弾きたい」と語っていた。私もきっとそれが正しいあり方なのだろうと長年思っていたのだが、この10年程になろうか、必ずしもそれほど硬くななスタンスを取らなくとも良いのではないかと考えを改めた。
バッハ作品の元の姿…オリジナル楽器による、できるだけ当時の演奏様式に近いと思われる演奏を追求することは大切だと思うが、一方で現代の楽器を使うに留まらず、様々な形での編曲も含め、引き継がれていくべき芸術であると考えている。
自分なりにバッハに近づく時、色々な道を通りつつも細かな奏法や相応しい古楽器を探すなど、究極的には全て超越しなければならないと考えた結果、最終的に「そこにあるものもので弾く」という結論に至った。現代のピアノで弾くことによって、バッハ時代の響きは生まれないかもしれないが、作品自体の内容や価値はその次元を遙かに超えている。あまり厳密に考え過ぎると、逆にバッハの作品の潜在力、生命力を限定することになると最近は考えている。
今回、改めて楽器の選択を考えた時、私にとって近い所にあり、また現時点で多くの人々にとっても自然で親しみがあると思われる現代のスタインウェイを使うことにした。
確かにカンタータ、受難曲はバロック・オーケストラで演奏するのが本来の姿ではあるけれど、素晴らしい現代の楽器によるオーケストラで、仮に若干のヴィブラートがあったり、ポルタメントがあったり、ピッチが多少高かったとしてそれを美しく聴かせてもらうのは、様式上のハイブリッド感があるかもしれないが、芸術的価値という意味で必ずしもマイナスばかりではないと私は思う。
無伴奏チェロ組曲でのカザルス、無伴奏ヴァイオリン・ソナタとパルティータでのブッシュ、エネスク、ミルスタイン、シェリングなどをバロック奏法ではないと言って否定することができるであろうか?
ヨーロッパの建造物で、例えばその一部はロマネスク様式、別の部分はゴシック様式の要素が含まれる、数世紀にわたって建造される建物は多く存在している。
古典的な言葉で書かれた文学の場合でも、現代語訳にしないと一般的な現代人の心には響かない、理解できないケースもある。
あと数百年も経てば、人々はきっと今とは全く異なる感覚でバッハを弾く、そして聴くことになるのだろう。
— ここでの演奏スタイルについて —
バッハには長年培われてきた伝統的な演奏法や考え方があり、一方で300年経った今でも新たな資料が発見され、次々と新たな楽譜や文献が刊行されており、新しい楽譜の読み方、様々な試行錯誤がなされている。
バッハの演奏様式、装飾音、テンポ、アーティキュレーション、アゴーギク、バロックの美学など様々なことが語られ、常に議論されている。
バッハ自身の書き残したものと当時のその地方での風習、息子と弟子たちが書き残した資料、その次の世代による記録等、複数の資料に異なる見解があるため、その異なる見解や法則が同時に適切、或いは不可とされうる場合にどうするのか、様々な憶測を生んでいる。
今回のレコーディングにおいては、アーティキュレーションや装飾音を極端にピリオド的、すなわち現代的な解釈にはしていない。またテンポも極端な遅さを避け、リズム的な躍動感を重視した。イネガル(不均等)の考え方を一部取り入れているが、チェンバロやクラヴィコートで弾く時ほどには取り入れていない。当時の楽器にはなかった、ソステヌートペダルを含む3つのペダルの使用も避けてはいない。数箇所程度ではあるが、20世紀前半までの(旧ソ連ではもう少し後まで)ピアニストが行なっていたベース音を1オクターヴ下の音で重ねる奏法も数カ所で試みている。
アーティキュレーションの考え方としては、現代ピアノでドライになり過ぎない程度に、適度に音型やモティーフが聴き取れるようにシェイプしているが、極端な細分化は避けている。
装飾音の考え方としては、あくまでも装飾音は装飾であることを前提として、19世紀から20世紀中頃までに培われてきた方法をある程度踏襲し、ノイマンやバドゥラ=スコダが論じている方向性に近いことをしているつもりである。特にプラールトリラーとトリラーに関しては、特に20世紀中頃からずっと提唱されてきた、上からの、そして拍に合わせるという規則正しいやり方だけではない可能性も模索している。
当然賛否については色々あるとは思うが、ピアノという楽器を使う以上、クラヴサン的なフランス風の典雅な装飾音よりは、若干北ドイツと南ドイツのオルガン流派やイタリア的な伝統に近い装飾音、シンプルで明瞭なハーモニーを感じられる装飾音を意識するようにした。
またテーマや対旋律の提示に装飾音がある場合、書かれているところ以外は何もつけないというドグマティックなやり方にはしていない。(そもそも装飾音は、多くの異稿譜で異なる場所についていることも多い。)
反行形の場合(装飾音の音型を反対にする場合も同様)も含め、殆どのケースで同じ場所に装飾を入れる様にしてはいるが、殊に音が太く伸びる現代のピアノにおいては、他の声部が込み入っていたり、或いは声部進行的にそれが不明瞭になったりする場合、ケースバイケースで若干異なるやり方を採用している。(例:第14番、第24番など)
基本的にプラールトリラーは4音として上から取ることが多いが、旋律線が不自然になると思われる場合や音型が既に装飾的な場合、シンプルな3音プラール(逆モルデント)や前打音にしており、他の声部との平行5度や8度が生まれる場合には、それを避ける策を幾つかの箇所で行っている。
あまり一般的とは言えないアプローチとして、装飾音の記号を必ずしも原典版の印刷譜通りにしていないケースもある。一例を挙げると第11番の前奏曲の楽譜には、トリルの異なる開始の仕方についての複数の記号が使われているが、もしもその通りにすると強い平行5度を感じるため、あえて装飾音の入れ方を統一させている。実は後述するトヴィーなどは、「バッハの原稿(1722年)には、その装飾音の書き方、種類に大変こだわりが見られるので、違うように弾くべきだ」と書いているが、その後のアンナ・マクダレーナ・バッハやアグリーコラによる手書き譜(バッハも一部それをチェックしていたと言われている)ではその違いがなくなり、また1755年前後に書かれたアルトニコルの原稿においてはほぼ統一した表記になっている。
また前述の通り、トリルは上から始まるという規則もあるが、必ずしもその通りには演奏していない。トリルが同じ作品の中で何度も出てくる場合、その規則は毎回同じ様に扱うことができず、特に和声上ベースラインには適応させられない場合もあり、主音から開始した方が自然な場合もあると考えた。(例:第16番)
他方、一部速いパッセージであっても、個人的に平行8度が気になるところなどに若干装飾を入れたりする試みをしている。(例:第3番、第9番、第19番など)
— 楽譜について —
以前、複数の大学でこの曲集をテーマに授業や演習を行った経験から、若い世代の多くのピアノ学習者の参考になるかもしれない、個人的に大なり小なり影響を受けたバッハ関係の著作を若干記させて頂きたいと思う。
バッハ愛好家の皆様にとっては常識的なものばかりとは思われるが、もしもまだお読みになっておられないものがあれば、少しずつでも紐解いていただければ幸いである。
この作品の楽譜は、昨今出版されている原典版だけでも大変な数になり、また過去の歴史的な校訂版も再版を繰り返しているものが多く、今でも数十種類を下らないエディションが手に入る。
バッハの楽譜を確立することの困難さについては言うまでもない。例え原典版であってもバッハ自身の原稿のみをベストとするのか、それともそれより後のバッハの妻や弟子たちによるコピー譜、バッハの修正も加味したものにするのか…などキリがない。余談ながら、現在ではネット上で自筆譜や同時代の手書き譜を家にいながらにして見ることができる、素晴らしい時代になった。
今回はベーレンライター版をベースにレコーディングを行ったが、幾つかの点で他の新旧ヘンレ版、ウィーン原典版などを参考にした所もある。(例:第22番など)
それらが広く一般的に使われている現在、過去の楽譜のことを書くのは時代錯誤と思われるかもしれないが、19世紀に出されたエディションの多くは、当時の状況やスタイルを知ることが出来て、興味深いもの、参考になるものが沢山ある。
そもそも1830年のメンデルスゾーンによる「マタイ受難曲」再演まで、バッハの伝統は途絶えていたため、19世紀時代のバッハは全てロマン派の価値観に染まったものであり正しくない、という様な単純な話ではないように私は思う。
ドイツ、特にライプツィヒを中心としてバッハの伝統は生き続けたのであり、バッハ存命中から18世紀終わりまでは多くの手書きによる写譜によってヨーロッパ中に伝えられ、1800年頃からバッハ作品の出版が複数の出版社によってほぼ同時に始まったのである。その時点では、バッハの息子達や周辺にいた弟子たちを知る音楽家もまだ生き残っており、その知識が何らかの形で継承されたと考えても不自然ではないだろう。
例えばグリーペンケールによるペータース社から出ているオルガン作品集に見られる解説は興味深い。
その流れから19世紀後半の生まれで20世紀中頃まで活躍していたドイツ系のピアニストたちの解釈、例えばフィッシャーによるバッハ作品の装飾音の解説なども、その根源を改めて考えてみる必要があると思われる。
パーマー版はとても面白い楽譜で、様々な音源によるフーガのテーマのアーティレーションの違いを論じた一覧表が付いている。解説は非常に参考になることも多いが、しかし装飾音については、論理的ではあるもののやや一元的な解釈に陥っているのではないかという気も少しする。
フォーレ/ロン版は、古風だがシンプルで雰囲気のある楽譜。要点を押さえた指遣いも丁寧。
チェルニー版は音に修正が多く、また表情記号やアーティキュレーションに関しても長いスラーが多く、すこぶる評判が悪い。しかし、幼少時の私も含め、この楽譜でバッハに親しんだ音楽家は過去に多数いた訳で、存在自体を簡単に否定するわけにはいかない。ベートーヴェンによるバッハの平均律の演奏に近いのではないかと言われる場合もあり、19世紀末以降の楽器には、案外うまく作用する場合もある。かつてブラームスが「音は正しくないが、フィンガリングは参考にすべき」と語った楽譜でもある。
ムジェリーニ版は、ボローニャを中心に活躍していた作曲家、ピアニスト、教育者による校訂版で、指遣いが非常に丁寧に選ばれており、「導入のための」使い易いエディションとして有名。100年前の楽譜だが、ありとあらゆる強弱、テンポ記号、クレッシェンドやデミニュエンドなどアイディア満載の楽譜で、装飾音についても一考に値する場合も多々ある。
バルトーク版は難易度順に容易なものから並んでいる。元々はハンガリーのピアノを学ぶ学生のために編纂された楽譜で、最小限の校訂とも言えるが、その最小限の強弱などの指示が面白い。
トヴィー版は解説が豊かで知的だが、ベートーヴェンのソナタの校訂版同様、言い方が回りくどく、現代ではなかなか読むのに一苦労する。
ビショッフ版は原典版が出てくる前の模範的な楽譜だったもので、細かい資料の読み方などは、現在でも通用する面があり有益である。
ブゾーニ版は、20世紀後半以降のSachlich(即物的)な世の中では大変評判の悪い楽譜だが、19世紀半ば生まれの作曲とピアノの巨匠の思考を辿ることが出来て大変興味深いもの。1巻と2巻では哲学が異なり、考え方の深化と簡潔化が見られる。
ライネッケ版は、ブライトコプフの学習版として出ていたもので、無駄な加筆がなく、記号による最低限のフーガの分析が含まれていること、フィンガリングも最低限ながら非常に適切で、譜割、譜面自体も非常に使いやすい。おそらく20世紀の初頭まではよく使われていた楽譜なのではないだろうか?そのまま再販を望みたい。
カゼッラ版は、ベートーヴェンのソナタの校訂譜と同じ様に、約80年前の中欧における音楽的な考え方とはどのようなものだったのかを知ることができる貴重な記録である。
日本においては、古くからチェルニーによる全音版と並び、井口基成による春秋社版が全国的に地方でも容易に手に入る楽譜として、昔から幅広く使われてきた。2022年に新装された井口版は遠山裕による詳細な解説が充実し、味わい深いものになっている。
2005年には細かな演奏指示のついた園田高弘版も出版された。前書きに書かれている考え方は非常にシンプルだが普遍的かつ個性的で素晴らしい。
2022年には野平一郎校訂解説の優れた楽譜が加わった。日本を代表する作曲家、総合的な音楽家、音楽的知性による分析が貴重で、2014年出版のインヴェンションとシンフォニアの楽譜に続く、日本の音楽界の宝物と言える。
— 解説書や著作などについて —
クヴァンツ、C. Ph. E. バッハ、L. モーツァルト、マールプルクなどを筆頭とする18世紀に出た様々な楽器の奏法の本は、常に重要な書物であり続けている。当時の文献なので修辞学と関係しており、法律の本の様な様相を見せるが、共通する考え方だけではなく矛盾している事柄もあり、様々な角度からの読み方が可能である。
そして20世紀初頭からのドルメッチ、カークパトリック、そして近年のアーノンクール、クイケン、コープマンなどの音楽家や研究者の著作も興味深いものであることは論を待たない。
演奏家としては、20世紀初期のシュヴァイツァー、ランドフスカ、フィッシャー、ギーゼキング、そして20世紀中期のトゥーレックやグールド、ヴァルヒャ、リヒター、レオンハルトなどは、特に録音を通してバッハを世界中の幅広い聴衆の元へ届けた。彼らのレコーディングが我々のバッハの聴き方に、そして後の世代の演奏家に大きな影響を与えているのは言うまでもない。
ケラー著「バッハのクラヴィーア作品」は日本語でも古くから翻訳されている古典的な著作。
バドゥラ=スコダ著「バッハ演奏法と解釈」は大変包括的な、バランスのとれた大著で、700ページにも及ぶ本ではあるが、翻訳も優れており、個人的にはとても共感するところが多かった。
ノイマン著「バロックとポストバロック期における装飾法」は、出版されてからかなり年月の経つもの。ノイマンの著作の日本語訳は一部のものしか出ていないと記憶するが、興味深い考察を多数含んでいる。
山崎孝著のインヴェンションとシンフォニアに関する本は、この曲集についての著作ではないが、バッハ作品全般とそれ以降数百年間の西洋音楽における鍵盤楽器の演奏様式について深く考えさせられる。真剣にピアノの勉強をしている学生全てにとって刺激となる良書だと思う。他のアジア言語にも翻訳されることを望みたい。
樋口隆一著、そして磯山雅著のバッハに関する著作は読み物としても面白く、偉大なる生活人バッハが生き生きと描かれている。
土田英介著「バッハ平均律クラヴィーア曲集 演奏のための分析ノート」は、全曲ではないが、フーガの分析本として、すべての角度から作品を照らし出す圧倒的な情報量で、存在価値は非常に高い。
小鍛冶邦隆著の「バッハ 平均律 解読」は、2024年1月に出たばかりの、洞察力に満ちた、親切心満載の素晴らしい新刊本。
シュターデ著のフーガの分析本は声部毎のスコアになっており、モティーフごとに記号がつけられ、その意味を明らかに映し出すわかりやすい分析本。但しドイツ語のみ。
— あとがき —
最後になるが、多くの友人がこの録音をサポートしてくれた。またいつも録音の際に万全な協力を頂いている三重県総合文化センター/三重県文化会館の梶吉宏さんとスタッフの皆様にも心から感謝を申し上げたい。
そして私に演奏の初歩や様々な鍵盤楽器への関心を持たせてくれ、2020年5月に他界した父にこのCDを捧げたいと思う。
2024年水無月 京都にて記す
上野 真