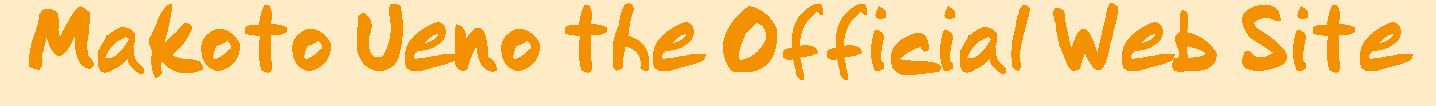Writings
ラフマニノフ雑感 その評価をめぐって
ラフマニノフとの最初の思い出深い出会いは1975年、私がまだ小学3年生の頃だった。これより2年ほど前、ラフマニノフ生誕100周年の記念LPアルバム「ラフマニノフの芸術」(1973)がRCAビクターから発売になり、音楽好きな両親が当時としてはかなり値が張るレコードを買ってくれた時だ。
このアルバムにはかなり充実した解説が付いていて、明治生まれの音楽評論家、例えば野村光一氏や属啓成氏が戦前のヨーロッパでラフマニノフを聴いた思い出を書いていたり、矢代秋雄氏のエッセイや、多くの興味深い写真があり、また端末の資料にはラフマニノフがRCAビクターのために録音したSPレコードの詳細な録音データが掲載されていた。
それまでも「ピアノ協奏曲 第2番」や「パガニーニの主題による狂詩曲」などは耳で聴いて朧げながら知っていたが、作曲者本人の圧倒的な演奏とその典雅な演奏スタイルに夢中になり、幼心ながらに感動したことを覚えている。
この記念LPアルバムは、SP盤の復刻とは言えとてもリアルな音で刻まれており、当時のストコフスキーやオーマンディ指揮のフィラデルフィア管弦楽団の芳醇濃厚なサウンドにはとても惹かれたものだった。ラフマニノフの演奏は、自作のみならずショパンやシューマンの演奏にも大いに魅力的なものに感じたのだったが、その当時の私は、かつてそれらが賛否両論、議論の的だったことを知る由もなかった。そしてクライスラーとのソナタ集…あの時代を生きた人間のみが持つ空気感、歌わせ方と表現のセンスがあった。
ちなみにこの体験は、その後、私が14歳で留学を志した際、伝説的な音楽家が多く活動していた都市だったということで、敢えてヨーロッパやニューヨークではなく、フィラデルフィアのカーティス音楽院を選ぶことにも繋がっている。
思えば、これが(1980年代以降に少しずつリバイバルしてきた)19世紀生まれの巨匠による、いわゆるRomantic Piano Playingに出会ったきっかけだったように思う。少しではあったが録音を残してくれた19世紀のピアニストたち、パハマン、ホフマン、コルトー、バックハウス、フリードマン、レヴィツキなどの演奏を聴き、当時の新しい世代のピアニスト(多くは1930~50年代生まれ)とは全く異なる音楽世界があることを意識し始めた。
その後、私は欧米各地で勉強してきたが、様々な作品や演奏の様式(スタイル)を考えた時、「ラフマニノフ」は、ある特定の流派、例えば第二次世界大戦後の中央ヨーロッパの厳格なスタイルから見ると、作曲家としても演奏家としても必ずしも認められない時期があったように思う。
私がヨーロッパで勉強していた1980年代後半であっても、まだラフマニノフというのは非常に表面的な音楽(家)だと論じる声がかなり残っていた。もちろんアメリカやイギリスなどでは愛好家も多く、偏見は相対的には少なかったが、アメリカの音楽家の中でさえ批判の声は多くあり、「お菓子のような音楽」、「ハリウッドの映画音楽」、「芸術性に欠ける」等と酷評するような音楽家や批評家がおり、私と同世代の学生仲間でも、ラフマニノフは美学的、道徳的に問題があると考えていた友人もいた。
そう言えばヒンデミットは彼の著書の中でチャイコフスキーを酷評していた。チャイコフスキーがモスクワ音楽院の学生の中で最も高く評価したラフマニノフが、いわゆるドイツ的、モラリスト的志向の強い音楽家に酷評されていたのも頷ける。
例えば私が尊敬する演奏家、クラウディオ・アラウやレオン・フライシャーは、ラフマニノフの演奏スタイルを表面的で深みのないもの、若い世代のピアニストにとって有害とさえ言えるものと捉え、そして作品のスタイルも好まなかった。私も一時期、その影響を受けていたこともありラフマニノフは全く弾かなかった。ロシアにおいてさえ、あのマリア・ユーディナはラフマニノフを好まなかった…おそらくアナトリー・ヴェデルニコフなども。
かのシュナーベルは、ラフマニノフがシューベルトの作品をまるで知らなかったと言って非難していたと同時に、ベートーヴェンのソナタを上手く弾くのは《自分の次に》ラフマニノフだ、と認めていたという。シュナーベルならではのウィットに富んだ話だが、特に当時の中央ヨーロッパ人にとって当然のことがロシア人にとってはそうでない場合もあり、受けた教育、背後にある文化の違いなどによって無理解を生む事実がある。時にラフマニノフが取った態度や話した事柄が誤解され、冗談のつもりで言ったことが真に受け止められるなど…名声と人気、そして富をも得た伝説的人物にはよくあることなのかもしれない。
しかしその後、長い年月が過ぎ、ラフマニノフの総合的な音楽家としての卓越した能力、作曲家のみならず指揮者、ピアニストとしてもすべての分野で一流であったこと、それは19世紀末までの大作曲家・演奏家の系譜に連なるものであり、今日ではかつてその様な酷評を受けていたことを識る若い世代の音楽家は少なくなって来た様に思われる。その70年の生涯の中で無調や12音などの前衛音楽から一定の距離をおいたスタイルを持ち、ロマン派の系譜に連なっていたことが、当時は賛否両論を起こしていたわけだが、21世紀に入り、彼は漸く全世界で肯定的に評価されるようになる。ラフマニノフ生誕150周年を過ぎた現在では、ピアニストに最も演奏される作曲家の一人となった。
歴史的なラフマニノフ演奏の「伝統」は、作曲者本人のみならず、ホロヴィッツ、ソフロニツキー、リヒテル、ギレリス、ルービンシュタイン、カペル、モイセイヴィッチ、アシュケナージなど第一級のピアニストたちが作りあげてきており、また他方、日本ではあまり広く知られていないがラフマニノフの解釈者としてムーラ・リンパニーやアール・ワイルドなどがいる。
私が4年間薫陶を受けた師匠ホルヘ・ボレット先生もラフマニノフを得意としていた。彼は学生時代からラフマニノフの演奏を何度もライヴで聴き、またアドバイスも受けた様で、その演奏は誰とも似ていない、少しでも聴けば他の誰とも間違えることのない固有のサウンド、歌い回し、テクニック、本当の意味での芸術的個性があった、と繰り返し話していたのを思い出す。そしてヨーゼフ・ホフマンと並び最高の演奏家だったといつも語っていた。
私がヨーロッパに渡ってからの師匠であったハンス・ライグラフ先生も、ボレットとはかなり異なる音楽的背景と趣味を持つが、ヨーロッパに客演していた1930年代のラフマニノフの演奏を聴いていたと語っていた。
ちなみにベネデッティ=ミケランジェリも、世界最高のピアニストの2人として、ラフマニノフとホフマンを挙げている。面白いのは、晩年には神聖なベートーヴェンの解釈者というイメージの強かったウィルヘルム・バックハウスが、若い頃はラフマニノフの作品を非常に高く評価していたという事実だ。
ラフマニノフは、自身の作品やレコーディングに対して極めて強い完璧主義を貫いていたらしく、「ピアノ協奏曲 第3番」のカデンツァは納得のいくまで数十回も繰り返し録音したなどの逸話が残っている。
クライスラーとラフマニノフが共演、録音したときの話も有名だ。クライスラーは、一度弾いたら既に満足するタイプだったが、ラフマニノフは満足せず、何度も何度もより良いものを探求し続けたという… 。二人とも最高の演奏家だったが、スタンスの違いが面白い。
これほどに質の高い作品を書き、同時にピアニストとして最高のピアニズムを持っていたラフマニノフは、20世紀前半、綺羅星のごとく存在したコンポーザーピアニストの中でも最も傑出した1人に違いなく、私自身としてはライヴでの演奏を聴いてみたかったものだといつも思っている。例えば1910年1月16日カーネギーホールでのマーラー指揮/ニューヨーク・フィルとの共演、そして1928年11月11日と12日におけるフルトヴェングラー指揮/ベルリン・フィルとの共演を聴いてみたかったものだ。或いはロシア在住時代、ラフマニノフの指揮でピアノ協奏曲を共演したホフマン、レヴィン、ジロティ、クロイツァー。モーツァルトやベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲を共演したイザイ。ドヴォルザークのチェロ協奏曲を共演したカザルス、などとのコンサートを録音でも良いから聴いてみたかったと思うのは私一人だけだろうか。
________________________________________
絵画的練習曲集 作品33(1911年夏作曲/1914年出版)と作品39(1917年出版)について
ラフマニノフの絵画的練習曲集(かつては練習曲集「音の絵」とも言われていた)は、ショパン、リスト、アルカン等の練習曲集の伝統を引き継ぎ、ただ単に指のエクササイズではなく、高度にピアニスティックであると同時に、芸術性、音楽的な表現の可能性というものを最大限に追求し、作曲家の個性が非常にわかりやすい形で表れている作品と言える。ほぼ同時期にドビュッシーの練習曲集(1916年出版)が生まれていることも興味深い。
本題から少し逸れるが、これらの練習曲集の前後に作曲された作品は次の通りだ。この時期にラフマニノフの興味、関心がどこにあったかが伺える。
交響曲 第2番 作品27(1906~08)
ピアノ・ソナタ 第1番 作品28(1907)
交響詩「死者たちの島」作品29(1909)
ピアノ協奏曲 第3番 作品30(1909)
聖金口イオアン聖体礼儀 作品31(1910)
(教会スラヴ語による4声の無伴奏合唱の為の聖体礼儀)
13の前奏曲集 作品32(1910)
6つの絵画的練習曲集 作品33(1911)
14の歌曲集 作品34(1912-15)
合唱交響曲「鐘」作品35(1913/1936改訂)
ピアノ・ソナタ 第2番 作品36(1913/1931改訂)
徹夜祷 作品37(1915)
6つのロマンス 作品38(1916)
9つの絵画的練習曲集 作品39(1917)
ピアノ協奏曲 第4番 作品40(1919-26/1927改訂/1941最終決定稿)
合唱とオーケストラのための3つのロシアの歌 作品41(1926)
コレルリの主題による変奏曲 作品42(1931)
パガニーニの主題による狂詩曲 作品43(1934)
交響曲 第3番 作品44(1936)
交響的舞曲 作品45(1940)
この中で興味深いのは、宗教的な作品(旧ソ連時代には演奏される事がほぼなかったらしい)が幾つかあること、合唱作品や歌曲集が多いことである。この中で作品34の歌曲集と作品38の歌曲集が特に示唆に富んでいる。
作品34は、バスからソプラノまでのすべての声の種類のために書かれている。これらは歌曲とは言っても、ピアノが多くの場所で主導権を握る形になっていて、それが魅力となっている。ラフマニノフの場合、様々な楽器や声楽、合唱のために自在に作曲することが出来た才人ではあるものの、ピアノという楽器が入った途端に(例えば交響曲がピアノ協奏曲になるだけで)、更に多彩な要素を持つ魅力的な作品に変貌を遂げる様に思われる。
作品34のタイトルは、
第1番「詩神(ミューズ)」
第2番「私達それぞれの魂の中に(私達誰の心にも)」
第3番「嵐」
第4番「過ぎ去るそよ風」
第5番「アリーオーン」
第6番「ラザロの復活」
第7番「それはあり得ない!」
第8番「音楽」
第9番「君は彼を知っ(てい)た」
第10番「私はあの日を覚えている」
第11番「小作農奴(聖なる旗を掲げて)」
第12番「何という幸せ」
第13番「不協和音(不調和)」
第14番「ヴォカリーズ」
作品38のタイトルは、
第1番「夕べに私の庭で」
第2番「彼女に」
第3番「ヒナギク」
第4曲「ハーメルンの笛吹き(ネズミ取り)」
第5曲「眠り(夢)」
第6曲「A-U(フランス語訳は頂に向かって)」
作品34や38における歌曲のタイトルは、言語によって若干異なるが、そのタイトルや詩の内容だけでも、彼が本質的にロマン派的な気質、詩人を愛する作曲家だったことがよく分かる。また全体として冬が長く夏が短い、静寂のある北国の自然の要素は無視できないだろう。
「絵画的練習曲集 作品33」の出版事情についてはやや複雑な経緯がある。作品23と32の2つの前奏曲集を書き終え、新たに練習曲集というジャンルに移行し、当初9つの作品を作曲した。1911年前後の作曲から、3年後の1914年の最初の出版の時点まで、自身の演奏会で取り上げ、その上で修正を施していったと言われている。しかし9つの練習曲を最終的には6曲に減らし、削除した内の1曲は、その後作品39-6として出版され、他の2曲、ハ短調とイ短調に関しては、ラフマニノフの生前に出版されることはなかった。
直前に6曲に減らした理由は不明だが、おそらくまた別の形で作品を使おうとの意図(遺作のハ短調の旋律は後年作曲された「ピアノ協奏曲 第4番」に使われている)や何らかの将来的な計画があったのかもしれない。確かに6曲の方が調性の関連性やキャラクターの重複が避けられているし、コンパクトに上手く纏まっている。
1914年の時点でモスクワのグートハイル出版社は、ドイツのブライトコプフ社と提携をしていたが、第一次世界大戦でそれが解消され、グートハイルはクーセヴィツキーのものとなり、1916年に再び出版されることとなった。
ラフマニノフの死後、1948年にはモスクワにある国営の出版社から遺作の2曲も加えた形で出版されている。長い間、ロシア版のリプリントや西欧諸国版(8曲または6曲)が入り乱れ、番号の統一もなく、それが作品33に関しての作品番号や順番の混乱を後世に残すこととなった。
このCDでは、ロシアで21世紀になってから出版された原典版や近年出版されたヘンレ版などを基に、あくまでも6曲の曲集として番号を付け、生前に出版されなかったものは遺作とし、CDの最後に2曲演奏する形とした。
「絵画的練習曲集 作品39」は、ロシア革命勃発により祖国を去ることを余儀なくされ、二度とロシアに戻ることがなかったラフマニノフが、ロシアの地で完成させた最後の作品。1916年夏から1917年春にかけて作曲、修正され、1917年の春に出版された。
作品33とは約5年ほどの隔たりがあるが、作品33に比べ作品39の方が全体的に作品の規模が拡大されていて、書法がより緻密になっていると言えるだろう。
この曲集はモスクワで出版されたが、出版したクーセヴィツキー自身が1920年に西側に移住したため、1920年にはベルリンでも出版されている。但しラフマニノフ自身が校訂に携わったのは1917年版までと考えられている。
作品33も39もヘ短調の和音で第1番が開始されるのは象徴的にも感じるが、作品33の方は通常通りヘ短調、しかしながら作品39の方はハ短調の作品でサブドミナントから始まる。
作品33の調性は、ヘ短調、ハ長調、変ホ短調、変ホ長調、ト短調、嬰ハ短調。
作品39は、ハ短調、イ短調、嬰ヘ短調、ロ短調、変ホ短調、イ短調、ハ短調、ニ短調、ニ長調。
ラフマニノフの作品中では珍しい長調の作品が、作品33は2曲あるが、第6番は出口の見えない不安と緊張感に満ちた葛藤(嬰ハ短調)で終わる。一方、作品39は8曲が短調で書かれており、第9番のみがニ長調として、根底にある暗さは保持しつつ混沌としてはいるものの行進曲風であり、祝祭的な雰囲気で終わる。
ラフマニノフの多くのピアノ作品はピアニスティックでありながら、同時に壮大なオーケストラ曲とも言える。作品の多くが様々な手によってオーケストレーションされ、この絵画的練習曲集も例外ではない。1930年にクーセヴィツキーは、イタリアの作曲家レスピーギにこれら2つの絵画的練習曲集から抜粋した作品をオーケストラのために編曲するようにと委嘱した。ラフマニノフ自身もこのアイディアに賛成して、非常に積極的にレスピーギとやりとりをした記録も残っている。現在知られている幾つかの曲についているタイトルは、レスピーギの編曲のスコア(作品160)にあるものである。レスピーギは5つの練習曲をまとめ「組曲」としてオーケストレーションを完成させており、順番は下記のようになっている。作品39-2「海とかもめ」、作品33-4 (従来の作品33-7)「祭りの情景」、作品39-7「葬送行進曲」、作品39-6「赤頭巾と狼」、作品39-9「行進曲」。
ラフマニノフは作品39を作曲した後、作品番号が付いていない編曲作品の出版はあるものの、次の作品40の「ピアノ協奏曲 第4番」を出版するまでは10年近くの月日が過ぎることとなる。それは、ラフマニノフが亡命ロシア人としての演奏活動、異国の地での生活を優先したからだと思われるし、その頃の殊にアメリカの聴衆の好みを反映し、そして3歳上のコンポーザーピアニスト、レオポルド・ゴドフスキーや、2歳下のコンポーザーヴァイオリニスト、フリッツ・クライスラーの影響もあって編曲作品がたくさん創られたからだと思われる。
経済的にも非常に裕福で、心の底からロシアの風土や生活を愛していた彼が、ロシアでの落ち着いた生活と経済基盤を全て捨てて、44歳になって祖国を去らなければならなかったのは、痛恨の極みだっただろう。
避け難い歴史の展開、1人の天才の生涯に「もし」はないが、もしもそのままロシアに居続けることが出来ていたならば、もしかすると更に多くの作品が生まれていたかもしれない。
最後に一つ付け加えておくと、よく言われる「交響曲 第1番」の初演の大失敗により、精神的な打撃を受け、立ち直るまで時間がかかった。それを克服して「ピアノ協奏曲 第2番」に結びついたというエピソードがある。それはある程度その通りなのだろうが、もしも交響曲の初演が成功し高い評価を得られていたとしたら、もしかしたらラフマニノフの作曲活動は少し異なるベクトルを向いて、もっと前衛的な作風に進んでいた可能性もあるかもしれない。
2025年6月京都にて
上野 真